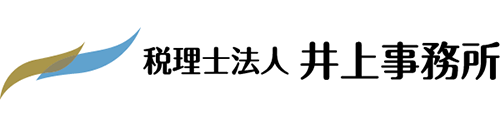家族の未来を繋げる相続対策、専門家と一緒に始めませんか?
相続対策は、大切な家族への想いを未来へ繋げるための重要なステップです。生前にしっかりと計画を立て準備を行い、家族とのコミュニケーションを大切にすることで、安心して次の世代に想いを伝えることができます。
では、財産を残す方が最も避けたいのはどんな状況でしょうか。それはやはり、自分が旅立ってから自らの財産を巡って家族内で相続争いが起きてしまうことではないでしょうか。ご自身の大切な家族だからこそ、ご家族全員で仲良く分け合いその財産を大切に使ってもらいたいという思いで、「相続争いが起きないようにしたいが、どうしていいかわからず悩んでいる」とご相談にみえる依頼者の方が大変多いです。
相続争いが起こってしまう理由の一つは、財産を継がせる方の意思がご家族に明確に伝わっていないことにあります。生前に自分の意思を家族に伝えることは、相続において非常に重要です。なぜなら、その意思の伝達が家族からの理解と納得を得る一つのきっかけとなることも多く、それが遺産の分配に関する家族間の意見の相違を未然に防ぐことに繋がるからです。
しかし、たとえ家族相手とはいえ、自分の財産を生前に伝えることにはどうにも抵抗を感じる方も多いでしょう。その要因としては、①持っている財産について、どの子に何を継がせて良いのか迷ってしまっていたり、②自らが持っている財産を赤裸々に語ることになってしまうため、気軽に相談できる相手が誰もいない、ということが挙げられます。税理士法人井上事務所では、ご本人のお気持ちを最優先にしたうえで、第三者として家族会議に参加し、作成した資料とともにお客様の想いを代弁することもできます。
私たちはこれまで数多くの相続申告を手掛けてきましたが、実際に相続が原因で家族が揉めてバラバラになってしまい、泣く泣く家庭裁判所で決着するというケースを何度も目にしてきました。相続前にご相談を頂くことで、こうした状況を未然に防ぎ、救えることもあるのではないかと感じています。
弊所が関わる相続案件では、可能な限り家族で争うことが一件もないようにすることを目指しています。相続税を減少させることも大切ですが、それ以上に家族の絆を保つことに重きを置いています。
相続後の指標を一緒に作り、家族の絆を保ちつつ、大切な方の意思を未来へと繋げる。それが税理士法人井上事務所の使命です。どんな小さな不安でも、お気軽にご相談ください。共に乗り越え、安心して次のステップに進むお手伝いをいたします。
具体的な生前対策
相続における生前対策としてご提案できる方法については、様々なものが考えられますが、代表的なものとして具体的には次のものが挙げられます。
(1)財産の把握
まずはお持ちの財産を全て正確に把握しなければ、どのような対策がよいのか検討することは難しいため、ご自身が所有している財産(不動産、預貯金、株式、保険など)の全体像を把握しリスト化します。
ここで特に問題となるのが、不動産や非上場株式など一見するだけでは具体的な金額のわからない財産です。例えば、預貯金については通帳の残高を見ればその金額を正確に把握できますし、上場株式についても市場での現時点での株価を見れば、その価値をほぼ正確に知ることができます。
しかし、不動産については、一見するだけですぐにその土地や建物の価格がわかるわけではありません。その金額をどのように評価するかという評価方法についてもいくつか存在しますし、どの評価方法を適用するのか、その土地が宅地なのか農地なのかなど様々な条件によって変わってきます。
また、非上場株式についても、その株式の価格は市場で決定されるわけではありませんので、インターネットで検索すればすぐわかるようなことはありません。その非上場株式を発行している会社の決算書をしっかりと読み込んでみなければ、その株式の一株あたりの価値がわかりませんから、その正確な金額を知ることはできないわけです。
このようなご自身では具体的な金額を判断しづらい財産についても、専門家としてしっかりと数字をお出しします。
(2)遺言書の作成
生前対策として、自らが持っている財産について、事前に遺言書を作成しておくという方法もあります。遺言書とは、自らの保有している財産について、死後どのように分けてほしいかという自身の意思を明確に記すためのものをいいます。被相続人が死亡したのちに遺言書がみつかった場合には、残された遺産については遺言に従って分けることが原則となりますので、家族間の相続争いが起きにくくなります。
この遺言については、法律上は3つの種類があります。1つ目が自筆証書遺言です。自筆証書遺言とは、遺言を残したい人が自ら紙に書いて残す遺言のことです。一般的に遺言書と聞いて最初にイメージするものが、この自筆証書遺言かと思います。しかし、この自筆証書遺言については、意外とその要件が法律により厳しく定められており、せっかく遺言書を作っても自分が亡くなった後に無効と判断されてしまい、結局それ自体が争いの種となってしまうことも少なくありません。
そこで、実務上は次の方式で遺言を残すことをおすすめされることが多いでしょう。それが、遺言の種類の2つ目である公正証書遺言です。公正証書遺言とは、公証役場において公証人に作成してもらう遺言のことをいいます。この公正証書遺言は、遺言のプロである公証人が作成するものであり、また、証人2人の立ち会いが必要となることから、正確性かつ確実性が高いものとなります。さらに、公証役場でその遺言書の原本を保管してくれるので、遺言書を紛失してしまったり、誰かが隠蔽してしまうリスクがありません。
税理士法人井上事務所では、お客様が遺言書を残すことをご希望の場合や、遺言書を作成した方がよさそうだと判断される場合には、この公正証書遺言の作成のお手伝いを致します。
(3)贈与の活用
ご自身が保有している財産の金額が多く、残されたご家族が多額の相続税を支払うことが予想される場合には、生前贈与が効果的であるケースがあります。生前贈与とは、ご自身が元気なうちに相続人らに事前に財産を贈与し、想定される相続税よりも少ない贈与税を支払うことにより、結果的に全体で支払う税額を縮小させる事をいいます。
例えば、贈与税の暦年課税方式では年間110万円の基礎控除があるため、年間110万円以下の贈与であれば贈与税はかかりません。
ただ、この生前贈与については、有効な生前対策として広く用いられてきたからこそ、税務署も目を光らせています。中途半端な知識により何となくの生前贈与をしてしまうと、自分が亡くなった後に税務署によりその生前贈与を否定され、せっかく贈与してきた財産が全て相続財産に持ち戻されてしまい、結局のところ相続税を満額近く支払うことになってしまうというケースも少なくありません。これでは、残される家族のために色々と考えて手を尽くしてきたつもりでも、結局のところ何の意味もなかったという結果になりかねません。ですので、生前贈与については、どのように贈与を行なっていくのが最適なのか、各人の資産状況に合わせた長期の計画を立てた上で、それに従って粛々と行なっていくことが重要となります。
自分の場合にはどのように生前贈与を行うことがベストなのか、事前に相続専門の税理士に必ずアドバイスを求めることをおすすめします。
(4)保険提案
実は保険についても相続の生前対策として利用できるものがあります。保険利用における一番有名な生前対策としては、生命保険の利用が挙げられます。
生命保険に関しては、預貯金をそのまま相続するのではなく、生命保険の保険金として受け取る場合は、「500万円×法定相続人の数」が非課税になるという非課税枠が設けられています。
ということは、自らが生命保険に加入して、保険金の受取人に法定相続人である家族を指定することで、上記非課税枠の部分については相続税がかからなくなるので、相続財産全体にかかる相続税を減らすことが可能になるわけです。
ただ、誰を保険契約者・被保険者・保険金受取人にするのか、という点など、加入すべき保険の契約内容に注意を要することもあるため、やはり専門家に相談したうえで正確に保険契約を締結しなければなりません。
(5)不動産の売却
ご自身がお持ちの財産について、土地や建物といった不動産ばかり複数所有しているが、預貯金についてはほとんどないという場合もあるかと思います。このような場合、いざ相続が発生すると、相続人としては「相続税を支払わなければならないが、税金の支払いに使える現金が手元にない」という事態が起こり得ます。こうなってしまうと、相続したご家族としては、財産を残してくれたことはありがたいけれど、相続税を支払うために金策に奔走しなければならないため、非常に苦労する状況に置かれてしまいます。
また、相続税の支払いについては、法律により「相続の開始を知ったときから10ヶ月以内に行わなければならない」とされています。相続が発生した際に行わなければならない相続手続きは多岐に渡ることから、この10ヶ月という期間は案外短く、すぐに到来してしまいます。となると、相続財産中にある不動産を売却して納税の資金を調達しようとしても、買い手も10ヶ月という期限が迫っていることがわかっていることから安値で買い叩かれてしまい、なかなか正規の価格で売却することが難しいという現状があります。
そのような状況を避けるために、お持ちの不動産について事前に売却をし、相続税を支払うことができるだけの資金を確保しておくという方法を取ることが望ましいケースもあります。ただ、これについては、不動産のまま所有しておく場合と売却してしまう場合と、どちらを選んだ方が相続税を安くできるのかという、相続時のその不動産の評価額との関連性がある問題にも繋がってきます。
どのような選択をすべきなのか、その不動産の性質・内容にもよりますし、そもそもご自身の資産状況にも大きく依存しますので、相続専門の税理士と打ち合わせの上で決めるようにしましょう。