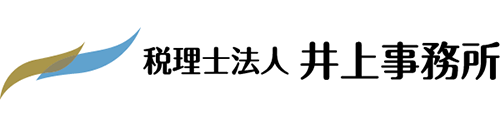人生で一度あるかないかの相続。その不安と困難を、井上事務所が全力でサポートし、解決します。
相続が発生した際、何から始めていいのかわからず戸惑うことが多いでしょう。相続は、多くの方にとって人生で一度経験するかどうかの特別な事象です。そのため、具体的な手続きや必要な書類についての知識が不足していることが多く、何をすれば良いのか分からない状態に陥りやすいです。また、相続手続きは膨大であり、必要な資料についても初めて聞くものが多く、身近に感じられないことが多いです。
さらに、日中仕事で忙しい方にとっては、相続の手続きを進める時間を確保するのが難しい現実があります。平日の昼間には仕事が優先されてしまうことが多いため、役所や金融機関に足を運ぶことが難しく、手続きが後回しになることも少なくありません。このような状況では、書類の提出期限や申告のタイミングを守ることが一層難しくなります。
加えて、相続手続きは心身ともに大きな負担を伴います。親族の喪失という深い悲しみの中で、複雑な手続きを進めるのは非常に辛いものです。相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に提出しなければなりませんが、この短い期間で必要な書類を揃え、申告を完了させるのは容易ではありません。
首尾一貫した手厚いバックアップ体制
相続手続きを迅速に進めることが、相続の成功の鍵です。こうしたお客様の問題を解決するために、税理士法人井上事務所は全面的なサポートを提供しています。手続きの流れを把握し、必要な書類の準備や提出を効率的に行うことで、お客様は精神的および肉体的な負担から解放され、スムーズに手続きを終えることができます。さらに、夜間や週末に対応可能なサポートを提供することで、忙しい方でも無理なく手続きを進めることができます。
井上事務所では、人生で一度あるかないかの相続税に関する不安と困難を共に乗り越えるパートナーとして、お客様一人ひとりに寄り添い、確実なサポートをお約束します。スケジュールを守ることが、相続手続きの成功において非常に重要です。
具体的なサポート内容
相続が発生すると、大切な方が亡くなられた悲しみの中で、遺産の分割や相続税の申告、各種資産の名義変更など、多くの手続きが必要となります。これらの手続きは財産の内容や相続人の状況によって異なり、行政機関や金融機関などとの多数のやり取りが必要となります。
当事務所で一般的にサポートしている内容は以下の通りです。
1 役所での手続き
①相続人の確認
相続手続きを行う場合、まずは誰が相続人になるのかを正確に確認しなければなりません。遺産分割協議と呼ばれる財産をどのように分け合うかの話し合いを行うにしても、相続人全員がその協議に参加していなかった場合には、その遺産分割協議は無効となってしまいます。ですから、最初に行う相続人を確認する作業はとても重要なものとなります。
相続人については、遺言がない限りは法定相続人がその地位につきますので、法定相続人が誰なのかを確認するために、市区町村役場に被相続人の戸籍の全部事項証明書や戸籍謄本等の取得を申請することになります。そして、この被相続人の戸籍については、戸籍を集める必要があります。
そうなると、この戸籍の取得の申請については原則として市区町村ごとに行う必要があるため、被相続人がその人生の中で全国を転々としているような事情があると、この戸籍の取得も一筋縄ではいかない作業となります。
②名寄帳の取得
被相続人が不動産を保有している場合、その不動産が存在している各市区町村に対し、名寄帳の取得を申請します。名寄帳とは、不動産についての固定資産税課税台帳を所有者ごとにまとめたもので、市区町村ごとに作成されています。ですので、名寄帳を取り寄せると、被相続人がその市区町村に保有している不動産が全て記載してあるわけです。
この名寄帳についても、戸籍謄本等と同じように各市区町村単位での管理となっているため、被相続人が複数の自治体に不動産を所有している場合、名寄帳の取り寄せ手続きも市区町村ごとにそれぞれ行うことになります。
役所での手続き
- 相続人の確認:戸籍謄本や住民票を取得します。
- 名寄帳の取得: 故人の所有の土地の把握を行います。
2 金融機関での手続き
①残高証明書の取得
亡くなった方の財産の中に銀行の預金口座がある場合、遺産の総額を確定させるために各金融機関に口座残高証明書の発行を依頼します。この口座残高証明書には、その金融機関に対して被相続人が保有している全ての口座とその残高が記載されているので、これを見ることで被相続人が保有している預金口座の残高を全て知ることができます。なお、これは金融機関ごとに依頼しなければならないため、多くの銀行や信用金庫に口座を保有している場合、それぞれ何通も発行依頼書を提出することになります。
②預金口座の名義変更
相続人間での遺産分割協議が全て終わり、遺産を分割する段階になると、遺産分割協議にて預金から金銭をもらうことになった相続人については、被相続人の口座から相続人自身へと分配手続きを行うことになります。この場合には、被相続人の口座を解約して払い戻された金銭を各相続人に分配する方法や、被相続人の預金口座を相続人の名義に変更する方法があります。
金融機関での手続き
- 残高証明書の取得: 金融機関から口座残高証明書を取得します。
- 預金口座の名義変更: 被相続人の預金口座の凍結を解除し、相続人へ分配手続きを行います。
3 自宅・会議室での手続き
①遺産分割協議
ご家族が亡くなった場合、亡くなった方の残した財産について、遺言が残されている場合には、原則としてその遺言書の内容に従います。しかし、遺言がない場合には、相続人の間で遺産をどのように分けるのかを決める必要があります。これを遺産分割協議といいます。
民法は、それぞれの相続人が相続できる遺産の割合について定めていて、これを法定相続分といいます。ただ、この法定相続分は遺産分割協議においてはあくまで目安となるものであり、これに従う必要はありません。相続人全員が同意さえすれば、どのような分割結果であっても有効な遺産分割協議として成立します。
ただし、遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があり、一人でも相続人が欠けている遺産分割協議で決定したことは、全て無効となります。
②相続税の試算のシミュレーション
上記①遺産分割協議を進める中で、「どのように遺産を分けると相続人それぞれがいくらの相続税を支払うことになるのか」という点について、複数のシミュレーションを作成します。
相続税については、「どの相続人が何をいくらもらうのか」によって、税額が大きく変わる場合があります。何をどのように分けたいかという相続人のご希望と、現実に支払うことになる相続税額との兼ね合いから、お客様ごとに最適な着地点を見つけ出すお手伝いを致します。
自宅・会議室での手続き
- 遺産分割協議: 故人の遺産をどのように分けるかを決めます。(相続人全員の合意が必要です。)
- 相続税の試算のシミュレーション:どのように遺産分割をすると、相続人各人がいくらの相続税を支払うことになるかを試算します。
4 証券会社での手続き
①株式評価証明書の取得
被相続人が上場株式や投資信託、国債などを保有していた場合、証券口座を開設している証券会社に対し、有価証券の残高証明書の発行を依頼します(保有している有価証券が投資信託や国債の場合は、銀行へ発行依頼をするケースもあります)。この残高証明書には、被相続人が保有していた株式など有価証券の種類や名称、数量、評価額などが記載されていますので、こちらを見ることで遺産における有価証券の評価額は全てわかることになります。
ただし、上場していない会社の株式(未公開株式)については、市場での取引価格が存在しないことから、証券会社に残高証明書の発行を請求するのではなく、税理士がその会社の決算書を精査し会社自体の財産評価をすることとなります。
②株式の名義変更
遺産分割協議の後、保有していた株式等の有価証券を相続人間で分配する場合、主に3つの方法があります。株式等の有価証券を取得することとなった相続人がその有価証券をそのまま取得する現物分割、株式を売却し売却資金を分配する換価分割、ある相続人が株式を取得する代わりに他の相続人に対価を支払う代償分割です。
このうち現物分割や代償分割をする場合には、被相続人が株式等を保有している証券会社を通じて、その株式の名義変更手続きを行ないます。この名義変更手続きを行うことで、株式の所有者が被相続人から相続人へと正式に変更されることになります。
証券会社での手続き
- 株式評価証明書の取得: 株式の残高証明書を証券会社から取得します。
- 株式の名義変更: 被相続人が保有していた株式の名義を相続人へ変更します。
5 税務署での手続き
①相続税申告書の作成および提出
上記で述べたように、相続手続きにおいては、まずは「誰が相続人になるのか」を確定し、次に「どのような相続財産がいくら残されているのか」を評価し、そしてそれを「どのように分けるのか」という遺産分割協議を行ない、その結果を遺産分割協議書として記します。
そして、この遺産分割協議書の内容に基づいて、相続税の申告書を作成し、税務署に提出します。そして、この相続税の申告書を提出した後に、申告書に記載の相続税額を納付することになります。
提出する税務署は、自分の家の近くの税務署というわけではなく、亡くなった方の最後の住所地とされているので、この点は注意が必要です。
また、相続税の納付については、現金で一括納付することが原則となります。仮に現金が足りない場合、相続税の支払いを年払いで分割払いにしてもらえる延納という制度もありますが、適用されるための要件が厳しく、簡単に使えるものではありません。ですので、この「税金を一括納付できるだけの現金を手元に用意しておくこと」を念頭に置いておかないと、納付の時点になって行き詰まってしまうことになりかねません。相続手続きにおいて、この相続税の納付までを見据えた相続専門税理士による一貫したサポートが重要となる所以は、まさにここにあります。
さらに、この相続税の納付までは、「亡くなった方の死亡日の翌日から10ヶ月以内に完了しなければならない」と法律で定められています。この10ヶ月という期間は、実際に相続人の立場に置かれてみるとかなり短く感じられ、バタバタしているうちに期限が来てしまうことも多いです。
②準確定申告
亡くなった方が自営業者や地主などで生前に一定額以上の収入があった場合、その年の1月1日から亡くなった日までに得た所得の金額を計算し、その所得にかかる所得税や消費税を申告・納付しなければなりません。これを準確定申告といいます。
通常の確定申告であれば、所得を得ている本人が毎年2月~3月に申告を行ない、所得税および消費税を納付しますが、準確定申告については、その所得を得ているご本人は亡くなってしまっているので、代わりに相続人が全員でこれを行う義務があるとされているわけです。
この準確定申告は、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内とされていて、この期限はかなり短く法定されています。
税務署での手続き
- 相続税申告書の作成および提出:相続税の申告書を作成し、それを税務署に提出します。
- 準確定申告:亡くなった方に生前収入があった場合、その方の年初から亡くなるまでの所得税および消費税の申告書を作成し、税務署に提出します。
6 法務局での手続き
①法定相続情報一覧図の取得
法務局では、法定相続情報一覧図を取得することができます。法定相続情報一覧図とは、被相続人の法定相続人が誰なのかを一覧にした家系図のようなものです。これを見ることで誰が法定相続人なのかが一目瞭然となります。
この法定相続情報一覧図を取得するメリットは、相続手続き全般において、上記「(1)①相続人の確認」で挙げた市区町村から集めた「戸籍謄本等の束」を用いる必要がなくなる点にあります(分厚い書類になってしまうことも多いです)。つまり、金融機関での預金の名義変更、証券会社での有価証券の名義変更、税務署での相続税申告・納税、不動産の名義変更等、広く相続手続き全般において、この法定相続情報一覧図という1枚の書面を提出するだけで、上記「戸籍謄本の束」を提出せずに済むようになるわけです。
なお、「だったら、そもそも戸籍謄本等の束の取得の手続きは不要で、初めからこの法定相続情報一覧図だけ取得すればいいのではないか」と疑問を持たれることもあるかと思います。しかし、この法定相続情報一覧図を取得する手続きの中で上記の戸籍謄本等が必要になりますので、結局のところこの戸籍謄本集めの手続き自体を省くことはできません。
②不動産の名義変更登記
被相続人が不動産を保有していた場合、遺産分割協議を経て当該不動産を取得することとなった相続人は、その不動産について、所有者の名義を自分へと変更する必要があります。この不動産の所有者の名義を変更する手続きは、相続手続きに伴い登記事項証明書に記載されている所有者の名義を変更することから、一般的に「相続登記」と呼ばれています。
この相続登記の手続きについては、法務局への申請によって行うことになりますが、法律により税理士が行うことはできません。しかし、井上事務所では、相続登記を得意分野としている信頼できる司法書士と提携していますので、弊所へご依頼いただくだけでワンストップでの一貫した対応が可能です。
法務局での手続き
- 法定相続情報一覧図の取得: 認証された一覧図の写しを法務局から発行を受けることにより、相続に関するさまざまな手続きに使用できます。
- 不動産の名義変更登記: 被相続人が所有していた不動産の名義変更登記手続きを行います。